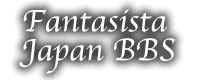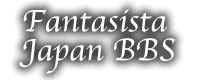| |
>基本的には個人で仕事してる場合は、たいていそういう感じなのではないでしょうか。
>それがサッカー選手でも。(プロスポーツ選手も区分上は個人事業主と同じですよね?)
おっと。
>サッカーの技術の中で、ゲームを見る目だとか時間の使い方であるとか周囲の選手への要求であるとか、チーム全体としての状況に応じた戦略的な意志統一であるとか、そうしたものって、強豪国はあの年代ですでにできている選手が多いですね。
これが頭にあったんですよ。
あの年齢で既にそういうことが解って、出来ている。そのためにはジュニアユース、それ以下の年代から、もうそういったことを考え、実行できるような「教育」ってのが行われていかなければならんですよね。
それを実現するための障害になりそうなのが、
>>物事の捉え方が表層的で、それが一般化している土壌だと実は大変なのかもしれないですよ、こういうのって。
じゃないかな、って思ったワケです。
地区大会での成績とか、そういうものを「指導者」の優劣を決める尺度にしちゃうと、選手をロボットにしちゃった方が即効性はあると思うんですよね。お前は開いとけ、この線から前には出るな、隣の選手とは何メートル以上は離れるな、とか。
指導者が選手に「自分で考える」力をつけさせていく、それを周りにいる人がどれだけ評価してあげられるか、そういうのも大事だな、と。
>指導者層は、もっとそうした評価軸を持って、選手を育成、指導して行かねばならないのではないか、と。
>あるいはマスコミ、ファン等ももっとそうした視点を持ってみるべきなのではないか、と。
あらもう書いてあった(笑)。そういうことです。
表層的だな、と思うことってサッカーでも多いんですよね。
「アーリークロス」ってもちろん味方にとっても「アーリー」なんですが、敵にとっても「アーリー」じゃないとあんま効果ないですよね。状況に応じて選択された「クロスボール」を評価しないと、いくら「この試合右からのクロスが何本」なんてやってもそれがなんなんだ、って思ってしまいます。
「ポストプレー」なんかもそう。誰も背負ってないのにFWがポストやって、敵のラインに突っ込んでいったところで味方がパス出す、笑わせるためにやってんのか、なんて。それを「ポストプレーは見事に決まったんですが・・・」とか言ってるとバカバカしくて。
|
|