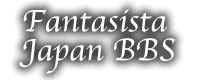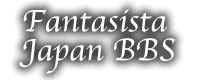| |
▼zukunasi_7さん:
>興味深いのは、道具の対応範囲を10回程度とし、対応できない物を20回とたとえている。
>さらにバージョンアップによる上積を1・2回としているあたりです。
少しトルシエ式に書きましたが、それが「戦いのステージが上がった」と言うことです。
ぼくがどうサッカーを捉えるかの問題ではなく、「どのような相手なのか」ということです。
すでに書いたように、相手のレベルが低かった時には棍棒を捨てる必要はさしてなかったのですから。
そして、いかにブラッシュアップしようと「決まり事」がある限りは読まれ、対応されるのです、そういうレベルの選手には。
そして、テレパシーでも使わない限りは「決まり事」なくして「道具」は使えないのです。
>私はたとえサッカーと言えども、1試合の中で全く予測不能の事態と言うのは、それほど頻繁には起らないと思っています〜(中略)〜
>ですからモデルケースを想定し、パターンを分類し、それらを選手に事前にインプットし、自軍の基本守備戦術に対応力・応用力を付加する事は可能と思います。
その通りだと思います。
そもそも攻撃なんていうのは、いくつかの典型的パターンを組み合わせて構築されるのです。
全く予測不能の事態がそんなに頻繁に起こるのなら、それはすごく面白い試合ですね。
でも実際はそんな楽しい試合はそれほどないし、そんな試合ができるチームもそれほどないでしょう。
大抵の場合のキモは、どういったケースでどういったパターンをいつどこでどのように組み合わせて使うか、に面白みもあるわけです。
実際には、予測できなくはないが、こちらの予測・反応の速度を上回られる、ということです。
だから、いくらシュミレートしても無駄です。
むろん、そういう速度をもシュミレートできるのならば別ですが、できないから強豪との実戦や高いレベルでの経験が必要なのですから。
そして、いくらモデルケースを想定し、パターンを分類してインプットしても、対応されれば同じことを繰り返さないのが一流です。
あるいは、「捨てプレー」としてひっかけに使うことだってあります。
だからこそ、選手個人の対応力、応用力が求められるのです。
そしてまた、どのようなシチュエーションでどのようなパターンでくるのかを予測・判断・反応するのは実戦の中での選手です。
それすらも簡単に分類でき、完全に予測できるチームなんてのは二流です。
98年の日本代表じゃないんですから(笑)
ここからは一般論として書きます。
文章の向かう先をズクナシさんに特定せず、話の流れから思ったまま書かせて下さい。
監督が、手取り足取り「こういう場合はこう守れ、こうなったらこうだ」などと全部教えなくてはならないのは、プロの代表クラスの選手にする指導じゃありません。
もちろん相手の特徴を捉え、いくつかの対応策を事前にやっておくくらいはどこのチームもやるでしょうが、基本的には戦術的に監督がやるのは、信号機を設置するまでであり、それを利用していかに上手に走るかは選手の考える事です。
「仮免許練習中」じゃないんですから。
うまく走るために時には赤信号をすっとばし、時には一時停止を無視もしなくてはなりません。
ピッチの上では積極的に自分で考えなくてはなりません。
うまく利用する、使えるときには使う、戦術なんてものはその程度のものでしょう。
だからトルシエも、「クレイジーが必要」だの、「戦術6割」だのと言うわけです。
戦うのは選手で、戦術ではありません。
戦術なんて選手次第でどのようにも変わってくるのです。
相手が何をしてくるのかパターン化して教えて欲しい、攻撃の手段を教えて欲しい、そんな選手は代表選手でもプロの大人の選手でもありません。
サッカーに「正解」はないのです。
雑誌で、風間氏が書いていました。
「バクスターから『ここ、一人でやってくれ』と言われて、『ああ、いいよ』と。彼はどうやれとは言いません。それはぼくが考えて結果を出せばいいんですから。外国人監督の場合は特に『こうやれ』とは言いません。やり方はいろいろありますよ」
「でも、優勝した当時の広島のメンバーでさえわからない人はけっこういましたよ。『で、どうしたらいいわけ?』と聞かれる。『どうにかするのは俺達なの!』って(笑)」
「あそこは風間ひとりにやらせよう」と決めるのが監督。それをどうやるか決めるのは選手。
それがプロの監督と選手。
こうしたことが常識でない日本は何かヘン。子供社会ですね。
だから「攻撃のパターンを教えてない」だの、ようちくさいことばっかり言ってる人がプロの解説者にまでいる。
監督は親ではありません。代表は中学校ではありません。
どこまで行っても個人がすべきことは個人がすべきことです。
戦術とは、それをやりやすくする手段にすぎないのですから。
プレイエリアが狭くなり、スピードが速くなり、求められるものが高精度にはなっても、個人が個人として局面でやるべきことには昔と大差はないのです。
|
|